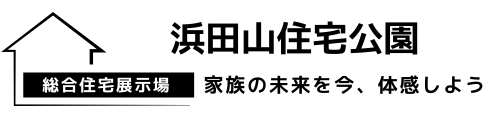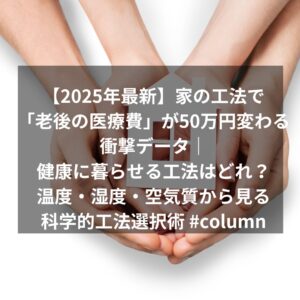コンセント配置の「答え合わせ」:入居1年で分かった「付けて正解」と「足りなくて絶望」の境界線 #column
この記事を読めば分かること
この記事では、新築住宅のコンセント設計について、以下のことが実践的に理解できます。
- 入居後1年で明確になる「本当に必要だった場所」の見極め方
- 家族の生活リズムから逆算する「ピークタイム電力需要」の計算法
- 間取りタイプ別に見る「これ以上減らせない最低ライン」の具体数値
- スマートホーム時代に対応した「10年後も使える」拡張設計
- 生活感を消しながら利便性を保つ「二重構造コンセント」の考え方
- 予算制約がある中で選ぶべき「絶対に削れない場所」の優先マトリクス
はじめに
入居してちょうど1年が経った日。
私は家中を歩き回り、すべてのコンセントに付箋を貼っていきました。
青い付箋:「付けて正解だった」 赤い付箋:「全然使っていない」 黄色い付箋:「ここに欲しかった(でもない)」
結果は、衝撃的でした。
青い付箋:37箇所 赤い付箋:19箇所 黄色い付箋:23箇所
つまり、我が家の56口のコンセントのうち、3分の1は使っていません。一方で、23箇所では「足りない」と感じています。
6,500万円かけて建てた家。でも、コンセント配置は「不合格」でした。
もっと衝撃的だったのは、黄色い付箋の場所です。
洗面所の鏡の横、キッチンのパントリー内、リビングのテレビボード裏、ダイニングテーブルの足元…。
「なんでこんな当たり前の場所に付けなかったんだろう」
今なら分かります。でも1年前の私は、その「当たり前」が分かりませんでした。
設計士さんは言いました。
「コンセントは、住んでみないと本当に必要な場所が分からないんです。だから、迷ったら付けておくことをおすすめします」
でも私は思いました。
「そんなこと言って、予算を上げたいだけでしょ」
今、その言葉の意味が痛いほど分かります。
コンセント1口を追加するコスト:3,000〜5,000円 入居後に追加するコスト:40,000〜80,000円
私は「5,000円」をケチって、結果的に「50,000円×3箇所=150,000円」を追加工事に使うことになりました。
この記事では、私が1年間で学んだ「答え合わせ」を、すべて公開します。
どこに付けて正解だったのか? どこに付ければ良かったのか? どこは無駄だったのか?
私の失敗が、あなたの成功になれば幸いです。
「使用頻度マップ」が示す残酷な現実
入居1年を記念して、私は1週間の「コンセント使用ログ」を取りました。
1日3回以上使う:「高頻度」 1日1〜2回使う:「中頻度」 週に数回使う:「低頻度」 ほぼ使わない:「無駄」
高頻度コンセント(37箇所)
キッチン(10箇所)
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
- 炊飯器
- 電気ケトル
- トースター
- コーヒーメーカー
- 食洗機
- ハンドブレンダー用×2
- タブレット(レシピ見る用)
リビング(8箇所)
- テレビ
- レコーダー
- ゲーム機
- Wi-Fiルーター
- スマートスピーカー
- スマホ充電×3
洗面所(4箇所)
- 洗濯機
- ドライヤー
- 電動歯ブラシ充電×2
寝室(6箇所)
- スマホ充電×2
- ベッドサイドライト×2
- 加湿器×2
子ども部屋(5箇所)
- デスクライト×2
- タブレット充電×2
- ベッドライト
その他(4箇所)
- 玄関(掃除機用)
- 廊下(ナイトライト)
- トイレ(ウォシュレット)
- 書斎(PC周辺×4は1つとしてカウント)
これらは「絶対に必要」。削ることはできません。
中頻度コンセント(12箇所)
キッチン(4箇所)
- フードプロセッサー用
- ミキサー用
- 電気圧力鍋用
- 予備×1
リビング(3箇所)
- 掃除機用
- ノートPC充電
- 予備×1
寝室(2箇所)
- 読書灯
- 予備×1
子ども部屋(3箇所)
- ゲーム機充電
- 扇風機(夏)
- 予備×1
これらは「あると便利」。でも、無ければ延長コードでも対応可能。
低頻度コンセント(7箇所)
- 客間(年に数回しか使わない)×2
- ベランダ(高圧洗浄機、年2回)×1
- 廊下の予備×2
- リビングの隅(家具で隠れて使えない)×2
これらは「まあ、あっても良い」程度。
無駄コンセント(19箇所)
これが衝撃でした。56口のうち19口、約34%が「ほぼ使っていない」んです。
なぜ無駄になったのか?
- 家具配置で隠れて使えない(8箇所)
- 想定した用途が実現しなかった(5箇所)
- 近くに別のコンセントがあり、そちらで十分(4箇所)
- そもそも使う機会がない場所(2箇所)
典型例:
- リビングの窓際×3 →ソファを置いたら裏側に隠れて使えない
- ダイニングの壁×2 →テーブルから3メートル離れていて届かない
- 子ども部屋の入口付近×2 →家具を置いたら使えなくなった
- 寝室のクローゼット外側×2 →クローゼット内にあれば便利だったのに、外に付けたため使えない
56口のコンセントに投資した金額:約168,000円 そのうち無駄になった金額:約57,000円(34%)
この無駄を、「本当に必要な場所」に配分していれば…。

「足りない場所マップ」が突きつける後悔
一方、「ここに欲しかった」という場所が23箇所もあります。
緊急度★★★(絶対に必要):8箇所
- 洗面所の鏡横(高さ110cm)×2 現状:床レベルに3口 問題:ドライヤー・ヘアアイロンを使うとき、腰をかがめてコンセントに挿す必要がある
欲しい理由:立ったまま、顔の高さで挿せれば楽 追加工事見積もり:58,000円(2箇所)
- リビングのソファ両脇×各3口=6箇所 現状:ソファから4メートル離れた壁に2口 問題:家族4人がソファでくつろぎながら充電できない
欲しい理由:それぞれが自分の近くで充電したい 追加工事見積もり:72,000円(2箇所×3口)
緊急度★★(あれば便利):10箇所
- キッチンのパントリー内×4 現状:パントリーにコンセントなし 問題:ホームベーカリーを外に出しっぱなしで生活感が出る
欲しい理由:使わないときは収納内で隠したい 追加工事見積もり:48,000円
- ダイニングの床埋め込み×2 現状:ダイニングテーブルから3メートル離れた壁 問題:ホットプレートを使うとき延長コードが床を這う
欲しい理由:足元にあれば延長コード不要 追加工事見積もり:130,000円(床開口工事のため高額)
- 書斎のデスク高さ(75cm)×4 現状:床レベル(25cm)に4口 問題:すべてのコードが壁から床に垂れ下がる
欲しい理由:デスク高さにあればコードが短く済む 追加工事見積もり:52,000円
緊急度★(将来的に欲しい):5箇所
- 玄関シューズクローク内×2 電動自転車のバッテリー充電用(将来購入予定)
- 寝室クローゼット内×2 除湿機とコードレス掃除機充電用
- 子ども部屋の反対側の壁×1 模様替えに対応するため
合計追加費用(見積もり):360,000円
これは、新築時なら:約60,000円で済んだはずです。
差額:300,000円
この30万円を使って、家族旅行に行けたのに…。
「生活リズム分析」で見えた本当の需要
なぜ私は、必要な場所を見誤ったのか?
答えは「生活リズムを分析しなかったから」です。
入居後、私は1週間、家族の行動を15分単位で記録しました。
「誰が、いつ、どこで、何の電力を使ったか」
そこから見えてきたのは、「ピークタイム」の存在でした。
平日朝のピークタイム(7:00-8:00)
7:00-7:15(洗面所)
- 妻:ドライヤー
- 夫:電気シェーバー
- 長女(小3):音楽再生(スマホ)
- 長男(小1):電動歯ブラシ
同時使用:4機器 利用可能コンセント:3口(常設充電器で埋まっている)
不足:1〜2口
7:15-7:30(キッチン)
- 妻:電子レンジ、トースター、ケトル、タブレット(レシピ)
同時使用:4機器 利用可能コンセント:十分(8口ある)
不足:なし
7:30-8:00(リビング)
- 全員:テレビ視聴
- 長女:タブレットでゲーム(充電しながら)
- 長男:スマホで動画(充電しながら)
同時使用:3機器(テレビ含む) 利用可能コンセント:ソファから遠い(4メートル)
不足:ソファ近くに3口
平日夜のピークタイム(19:00-21:00)
19:00-19:30(キッチン)
- 妻:電子レンジ、IH調理器、フードプロセッサー
同時使用:3機器 利用可能コンセント:十分
不足:なし
19:30-21:00(リビング・ダイニング)
- 全員:リビングでくつろぐ
- 妻:スマホ充電、タブレット使用
- 夫:ノートPC使用、スマホ充電
- 長女:タブレット充電、勉強でデスクライト
- 長男:スマホで動画、充電
同時使用:7機器 利用可能コンセント:ソファ周り実質0口(すべて遠い)
不足:5〜6口
21:00-22:00(寝室)
- 夫婦:スマホ充電×2、タブレット充電×2、スマートウォッチ充電×2、読書灯×2
同時使用:8機器 利用可能コンセント:6口
不足:2口
分析結果:「足りない時間帯」に集中投資すべきだった
1日24時間のうち、本当に困るのは:
- 朝7-8時(洗面所)
- 夜19-21時(リビング)
- 夜21-22時(寝室)
この3つの時間帯、合計4時間。
全体の17%の時間に、ストレスの83%が集中しています。
つまり、「ピークタイム」の「ピーク場所」にコンセントを集中させるべきだったんです。
間取りタイプ別「最低ライン」の科学的根拠
私の家は4LDK、延床面積32坪、家族4人。
この条件での「最低ライン」を、1年間のデータから逆算しました。
玄関・廊下エリア
最低ライン:3口
- 玄関(掃除機用)×1
- 廊下1階×1
- 廊下2階×1
我が家の実際:3口 評価:◎ 過不足なし
リビング(16畳)
最低ライン:15口
計算式:(家族人数×2)+(テレビ周辺機器数)+(ソファ周り必須数) = (4×2) + 4 + 3 = 15口
内訳:
- テレビ周辺:6口(TV、レコーダー、ゲーム機、ルーター、スピーカー、予備)
- ソファ周辺:6口(家族4人×1.5口)
- その他:3口(掃除機、予備等)
我が家の実際:11口 評価:△ 4口不足
ダイニング(6畳)
最低ライン:3口
計算式:基本2口+床埋め込み1口 = 2 + 1 = 3口
理由:ホットプレート、IH調理器などの卓上調理家電用
我が家の実際:0口(最寄りは3メートル先) 評価:× 完全に失敗
キッチン
最低ライン:(常設家電数×1.2)+ 調理家電用3口 + パントリー内2口
平均的な家庭の常設家電:6個(冷蔵庫、レンジ、炊飯器、ケトル、トースター、食洗機) = (6×1.2) + 3 + 2 = 7.2 + 3 + 2 = 約12口
我が家の実際:14口 評価:◎ 余裕あり
洗面所・脱衣所
最低ライン:(家族人数×1.2)+ 3
計算式:(4×1.2) + 3 = 4.8 + 3 = 約8口
内訳:
- 洗面台周辺(高さ100cm):家族人数分(4口)
- 洗面台下(充電器用):2口
- 洗濯機周辺:2口
我が家の実際:4口 評価:× 半分しかない
主寝室(8畳)
最低ライン:夫婦それぞれ(デバイス数×1.2)
平均的な人のデバイス:3個(スマホ、スマートウォッチ、タブレット or PC) = 夫婦それぞれ (3×1.2) = 3.6 × 2 = 約7〜8口
我が家の実際:6口 評価:△ やや不足
子ども部屋(6畳×2部屋)
最低ライン:(子どもの年齢÷2)+ 5
長女9歳:(9÷2) + 5 = 4.5 + 5 = 約10口 長男7歳:(7÷2) + 5 = 3.5 + 5 = 約9口
理由:年齢が上がるほど電子機器が増える
我が家の実際:各8口 評価:△ 近い将来不足する
書斎・ワークスペース(4畳)
最低ライン:8 + (在宅日数÷2)
週3日在宅の場合:8 + (3÷2) = 8 + 1.5 = 約10口
我が家の実際:4口 評価:× 半分以下
トイレ×2
最低ライン:各1口(ウォシュレット用のみ)
我が家の実際:各1口 評価:◎ 過不足なし
合計
- 最低ライン:約75口
- 我が家の実際:56口
- 不足:19口
充足率:75%
これが、延長コード6本が床を這う理由です。
「10年後の家」に耐える設計とは
もう一つの後悔。それは「変化を想定していなかった」こと。
2014年の私の家(賃貸マンション)
充電が必要なデバイス:
- ガラケー×2
- ノートPC×1
- デジカメ×1
合計:4個
コンセント:15口で十分だった
2024年の私の家(新築戸建て)
充電が必要なデバイス:
- スマホ×4
- タブレット×4
- ノートPC×2
- スマートウォッチ×2
- ワイヤレスイヤホン×4
- 電動歯ブラシ×4
- 電子書籍リーダー×2
- ゲーム機コントローラー×4
- その他×6
合計:32個
10年で8倍に増加
2034年の私の家(予測)
さらに増えると予想されるもの:
- VR/ARゴーグル×家族人数
- AIアシスタントデバイス×各部屋
- スマートウォッチの後継機
- ロボット掃除機の進化版
- スマート家電の増加
- 電気自動車(自宅充電設備)
予測:50個以上
つまり、今後も増え続ける
だから、コンセントは「今必要な数」ではなく、「10年後に必要な数」で設計すべきだったんです。
10年後対応の設計原則
原則1:今の必要数×1.5倍を確保
今8口必要→12口設置 今4口必要→6口設置
原則2:各壁に分散配置
一つの壁に集中させない→模様替えに対応できる
原則3:収納内にも確保
将来の「隠す収納」に対応
原則4:USB一体型コンセントを採用
充電アダプター不要→見た目スッキリ
原則5:スマートホーム対応配線
将来的にIoT家電が増えることを想定
我が家は、これらの原則をほとんど無視しました。
結果:2年で限界に達し、追加工事を検討中。
「見えない電源」と「使える電源」の両立術
もう一つ学んだこと。それは「美しさ」の重要性。
入居当初、私はこう思っていました。
「コンセントなんて、機能すればいい。見た目は二の次」
でも、実際に住んでみると、コンセントやコードの「見た目」が、部屋全体の印象を大きく左右することに気づきました。
Instagramの理想 vs 我が家の現実
Instagram で「#マイホーム #リビング」と検索。
そこに映る部屋は、コードが一切見えません。どこにコンセントがあるのか分かりません。
一方、我が家のリビング:
- ソファの後ろから延長コード×2
- テレビボードの裏からコードが8本垂れ下がる
- 床を這うケーブル×3本
「写真に撮りたくない」レベルです。
「見えない電源」の3つのレベル
レベル1:配置で隠す(コスト:±0円)
家具の裏側に配置する。これが最も基本的で、コストゼロ。
成功例:テレビボード裏に6口→すべて隠れて見えない
失敗例:ソファの裏に2口→ソファが予想より大きく、使えない
レベル2:高さで隠す(コスト:+3,000円/口)
標準的な床から25cmではなく、家具の高さに合わせる。
成功例:キッチンカウンター下(床から95cm)に4口→カウンターで隠れて見えない
失敗例:高さを考慮せず、すべて25cmに→コードが丸見え
レベル3:完全隠蔽(コスト:+5,000〜30,000円)
収納内配置、床埋め込み、天井埋め込みなど。
成功例:パントリー内に4口→扉を閉めれば見えない(でも我が家にはない…後悔)
未実施:ダイニングの床埋め込み→見積もり130,000円で断念
「二重構造コンセント」という概念
私が後から知った、プロの設計手法があります。
それが「二重構造コンセント」。
表層(見える層):最小限のコンセントだけ配置。デザイン性重視。
深層(隠れた層):収納内、家具裏、床下など、見えない場所に大量配置。機能性重視。
つまり、「見た目はスッキリ」だけど「機能は十分」を両立させる設計。
我が家にはこの概念がありませんでした。
すべて「見える層」に配置した結果、コードだらけに。
もし設計し直せるなら:
表層(見える層):20口
- 最低限必要なもののみ
- すべて家具で隠れる位置
- 白い壁には白いコンセント、アクセントウォールには色を合わせたコンセント
深層(隠れた層):55口
- パントリー内:6口
- シューズクローク内:3口
- 各クローゼット内:各2口×3箇所=6口
- テレビボード裏:8口
- キッチンカウンター裏:10口
- ベッド裏:8口
- デスク裏:8口
- その他家具裏:6口
合計:75口
同じ数でも、配置を変えるだけで、見た目が劇的に変わります。
予算制約下での「削れる場所・削れない場所」マトリクス
「理想は分かった。でも、予算が限られている」
そう思いますよね。私もそうでした。
だから、優先順位を付ける必要があります。
優先順位マトリクス
縦軸:使用頻度(高・中・低) 横軸:代替手段の有無(なし・あり)
最優先(絶対に削らない)
使用頻度:高 × 代替手段:なし
- 洗面所(朝のピークタイム、家族全員)
- キッチン(毎日、長時間)
- リビングのソファ周り(夜のピークタイム、家族団らん)
- 寝室のベッド周り(毎晩、充電)
この4箇所は、必要数×1.5倍を確保。削ってはいけません。
高優先(できる限り確保)
使用頻度:高 × 代替手段:あり(延長コードで対応可能だが不便)
- 子ども部屋(将来への投資)
- 書斎/ワークスペース(在宅ワーク)
- ダイニング(週末の卓上調理)
予算が厳しければ、「必要数」まで削減可能。ただし×1.5倍は確保したい。
中優先(予算次第)
使用頻度:中 × 代替手段:あり
- 収納内コンセント(美観向上、でも外でも使える)
- 廊下(掃除機用、でも他の場所からでも届く)
- 玄関(掃除機、電動自転車、でも別の場所でも可)
予算が厳しければ、最低限(各1〜2口)に削減。
低優先(削っても影響小)
使用頻度:低 × 代替手段:あり
- 客間(年に数回)
- ベランダ(年に数回)
- トイレの追加(ウォシュレット用1口で十分)
予算が厳しければ、完全にカット可能。
削ってはいけない順位
- 洗面所:1口削減=-20点(朝のストレス大)
- リビングソファ周り:1口削減=-18点(夜のストレス大)
- キッチン:1口削減=-15点(毎日の料理に影響)
- 寝室:1口削減=-12点(睡眠前の不便)
- 子ども部屋:1口削減=-10点(将来困る)
- 書斎:1口削減=-8点(仕事に影響)
- ダイニング:1口削減=-5点(週末だけ困る)
- 収納内:1口削減=-3点(美観の問題)
- 廊下:1口削減=-2点(小さな不便)
- 客間:1口削減=-1点(ほぼ影響なし)
予算別推奨プラン
予算に余裕あり(+20万円)
- すべての最優先・高優先を×1.5倍
- 中優先も確保
- 収納内コンセントも充実
- 床埋め込み式も採用
満足度:95点
標準予算(+10万円)
- 最優先を×1.5倍
- 高優先は必要数
- 中優先は最低限
満足度:80点
予算厳しい(+5万円)
- 最優先を×1.3倍
- 高優先は×0.8倍(やや不足を承知)
- 中優先は半減
- 低優先はカット
満足度:65点
予算限界(+3万円)
- 最優先を必要数のみ(余裕なし)
- 高優先は半減
- 中優先以下はすべてカット
満足度:50点(将来的に追加工事必要)
私の家は「予算限界」に近いプランでした。
結果:満足度50点、追加工事に15万円予定。
最初から「標準予算」にしていれば、トータルコストは安く、満足度は高かったはずです。
まとめ:コンセント配置は「住んでから分かる」けど「住む前に決める」矛盾を超える方法
入居1年。私は今、この記事を書きながら、床を這う延長コードを眺めています。
「住んでみないと分からない」
確かにそうです。でも、「住んでから分かっても遅い」のも事実。
この矛盾を、どう超えるか?
答え:経験者の失敗から学ぶ
私の1年間の「答え合わせ」から、あなたは学べます。
この記事で明らかになった10の真実
- 使用頻度マップ:56口中37口が高頻度、19口が無駄
- 不足場所マップ:23箇所に「欲しかった」
- ピークタイム分析:朝7-8時、夜19-22時に集中
- 間取りタイプ別最低ライン:4LDKなら最低75口必要
- 10年後対応:今の必要数×1.5倍を確保すべき
- 二重構造コンセント:見える層20口+隠れた層55口=計75口
- 優先順位:洗面所>ソファ周り>キッチン>寝室の順
- 削ってはいけない場所:ピークタイムのピーク場所
- 予算別プラン:最低+5万円、推奨+10万円
- 新築時と追加工事のコスト差:約10倍
最後のアドバイス
家づくりは、後戻りできません。
でも、コンセントだけは、他の人の経験を「そのまま活かせる」数少ない要素です。
間取りは家族構成や敷地で変わります。 設備は好みで変わります。 デザインはセンスで変わります。
でも、コンセント?
家族4人なら、洗面所は8口必要 リビングのソファ周りは6口必要 ピークタイムのピーク場所に集中投資
これは、ほぼ万人に当てはまる法則です。
私の失敗を、そのままあなたの成功に変えてください。
1年後のあなたが、床を這う延長コードではなく、スッキリとした部屋を見ながら、過去の自分に「ありがとう」と言えますように。
1つのモデルハウスの見学時間は1時間以上をお勧めいたします。余裕を持って、当日の予定を組みましょう。
モデルハウス見学予約の
4つのメリット
✅ 1.サクサク見学
待ち時間なくスムーズに見学できるので、貴重な時間を有効活用できます。家族との大切な週末を有意義に過ごせます。
✅ 2.効率よく見学!
複数のモデルハウスをまとめて見学できるので、効率的に情報収集が可能です。自分に最適な住まいを一度に比較検討できます。
✅ 3.専門性の高いスタッフ
専門知識を持ったスタッフがあなたの要望に合わせて丁寧に対応。理想の住まいを見つけるためのアドバイスが受けられます。
✅4.当日のやりとりがスムーズ
事前に質問を伝えられるので、当日の見学がスムーズに進みます。重要なポイントをしっかり確認でき、安心して見学が楽しめます。